今回は、良くも悪くも睡眠薬の王道であった「ベンゾジアゼピン系の睡眠薬」について説明します
ベンゾジアゼピン系の睡眠薬というのは、
ハルシオン(トリアゾラム)
レンドルミン(ブロチゾラム)
サイレース、ロヒプノール(フルニトラゼパム)
ドラール(クアゼパム)
などが挙げられます。
*商品名(一般名)です。
ただ、最近では、
その理由やメリット、デメリットを説明いたします。
目次
不眠症の原因と脳の興奮系・抑制系バランス
不眠は、以下のような様々な原因によって引き起こされます。
ストレス(仕事、人間関係、家庭、学校など)
アルコール摂取
薬の服用
精神疾患(うつ病、躁うつ病など)
生活習慣病
これは、以前のブログでも説明いたしました
あわせて読みたい


【精神科医が解説】不眠の対処法〜原因と種類〜
誰でも一度はベッドや布団で横になるものの「寝れない...」という経験はあると思います。 夜根レナさん 最近、寝つきが悪くて「寝れない、寝れない...」と思う...
脳内には、「興奮系」と「抑制系」の神経が存在しています。
通常はバランスよく存在していますが、

不眠症では脳の興奮系が優位になっているため寝ることができなく
脳の中では、情報をやり取りする際に、
神経から神経へ神経伝達物質をパスしてキャッチすることで、
神経伝達物質の中で、興奮系には「オレキシン」
GABAとは
GABAは、
量だけでみればグルタミン酸という物質が最多なのですが、
GABA入りのチョコレートなどが売っていますが、
ベンゾジアゼピンとGABAの関係
ベンゾジアゼピン系のお薬は昔から抗不安薬や睡眠薬で広く使われ
受容体とは、

ベンゾジアゼピン系のお薬は、
ベンゾジアゼピン系睡眠薬のメリットとデメリット
ベンゾジアゼピン系のお薬のメリットは、
・即効性がある
・不安や催眠だけでなく、
デメリットとして、
・眠の質が落ちる
・ふらつき、翌朝への持ち越し、健忘(物忘れ)
・転倒のリスクがある(特に高齢者)
・耐性(効果が薄れてくる)や依存性(やめられなくなる)がある
最大のメリットとしては、飲んですぐに効果を実感できる「
結果として、
ベンゾジアゼピン系睡眠薬の副作用
ベンゾジアゼピン系の睡眠薬には、
精神神経系症状
一過性前向性健忘
依存性
それぞれ順番に解説します。
精神神経系症状
精神神経系症状とは、ふらつきや頭痛、
ベンゾジアゼピン系睡眠薬には、
そのため、服用後は速やかに就寝の準備を行うとともに、
特にご高齢の方は、もともと筋力が弱っていますので、
ほかにも、
このような副作用が見られた場合は、担当医に相談した上で、
繰り返しになりますが、
転倒リスクの高いご高齢の患者さんは中止か変更を検討すべきです
一過性前向性健忘
一過性前向性健忘とは、
服用した本人は寝たつもりだったとしても、
記憶を失っているためまったく自覚が無い行動をした形跡が翌朝に
服用した本人は、行動のコントロールをすることができないため、
ですから、介護の負担が増大するケースがあります。
特に、
依存性
ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、
睡眠薬の依存症には大きく分けて、
精神的依存とは、
一方で、身体的依存とは、
上でご説明したように、
その刺激があることに身体が慣れてしまうことで、
不調には、頭痛やふらつきなどの身体的不調だけではなく、
できる限り依存を防ぐためにも、
ベンゾジアゼピン系睡眠薬の種類
主なベンゾジアゼピン系の睡眠薬として、
ハルシオン(トリアゾラム)
レンドルミン(ブロチゾラム)
サイレース、フルニトラゼパム(フルニトラゼパム)
ドラール(クアゼパム)
が挙げられます。
それぞれについて説明します。
ハルシオン(トリアゾラム)
ハルシオンは、
個人差はあるものの、服用後10~30分後には眠気を感じられ、
非常に効果が高い睡眠薬である一方で、
また、超短時間作用型であり、
依存を加速させないためにも、少量での服用開始や、
<メリット>
即効性が期待できる
入眠障害の効果が強い
翌朝の眠気が少ない
ジェネリックが発売されている(薬価がリーズナブル)
<デメリット>
作用時間が短い(中途覚醒や早朝覚醒に効果が乏しいことがある)
健忘の副作用に注意が必要
依存性が高く、減量が困難
乱用されることがある
昔から処方されているお薬ですが、
依存状態で切るに切れない状況が長年続き、
ご家族が睡眠薬を飲んでいる場合、
特に高齢になればなるほどリスクは高まるので、
レンドルミン(ブロチゾラム)
レンドルミンは、
ハルシオンに比べて、作用時間が長いため、
また、筋弛緩作用や抗不安作用が認められており、
薬の強さは他の睡眠薬と比べて標準的ではあるものの、
<メリット>
即効性が期待できる
入眠障害に有効
中途覚醒や早朝覚醒にも有効
ジェネリックが発売されている(薬価がリーズナブル)
<デメリット>
眠気(翌朝への持ち越し)の副作用に注意が必要
ふらつきの副作用に注意が必要
筋弛緩作用から睡眠時無呼吸が悪化することがある
依存性に気を付ける必要がある
高齢者でせん妄を生じることがある
私が研修医のころは、不眠患者さんがいれば、入院でも外来でも「
しかし、高齢者ではせん妄を発症したり、
薬や環境の変化などから時間や場所が急にわからなくなることを言
サイレース、ロヒプノール(フルニトラゼパム)
サイレース、ロヒプノール(フルニトラゼパム)は、
中間作用型であるため、睡眠時間全体に効果が認められ、
サイレースの効果は非常に強く、
しかしながら副作用や依存性についても注意が必要で、
非常に強力であるため、処方されることは滅多にありません。
<メリット>
即効性が期待でき、効果が強力
入眠障害に有効
中途覚醒や早朝覚醒にも有効
ジェネリックが発売されている(薬価がリーズナブル)
注射剤が発売されている(興奮が激しい入院患者さんに使われる)
<デメリット>
眠気(翌朝への持ち越し)の副作用に注意が必要
ふらつきの副作用に注意が必要
筋弛緩作用から睡眠時無呼吸が悪化することがある
依存性に気を付ける必要がある
高齢者でせん妄を生じることがある
海外旅行で注意が必要(持ち込み禁止の国がある)
もうほぼ新規で処方することはなくなりました。
他院でこの薬を出してもらえないために、
私は決して処方しませんが…
ドラール(クアゼパム)
ドラールは、長時間型のベンゾジアゼピン系睡眠薬であり、
作用時間が非常に長いので、
そのため、
ドラールは上述した3種類の睡眠薬と比べても、
ただし、作用時間が長い分、
<メリット>
即効性と強い効果が期待できる
入眠障害に有効
中途覚醒や早朝覚醒に有効
抗不安効果が期待できる
離脱症状が少ない
ジェネリックが発売されている
眠気(翌朝への持ち越し)の副作用に注意が必要
ふらつきの副作用に注意が必要
筋弛緩作用から睡眠時無呼吸が悪化することがある
睡眠時無呼吸症候群で使えない
高齢者でせん妄を生じることがある
食後に服用すると急激に吸収されてしまう
ジェネリックの割に薬価が高い
私はドラールも処方することがほぼないです。
長時間作用することのデメリットが多いとおもいます。
まとめ
ベンゾジアゼピン系睡眠薬の概要や主な副作用、
ベンゾジアゼピン系睡眠薬は効果が強力なものが多い分、
いまでは、
そのため、処方する機会も減ってきて、第一選択として、
漫然と内服していると、依存や耐性も出てきます。
とくに高齢者は年齢とともに副作用が出やすくなり、
何を飲んでいるのかしっかりと自分自身で把握し疑問がある場合は
また、高齢者は何を飲んでいるのかさえ、無頓着になっています。







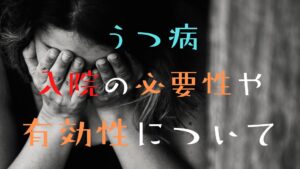
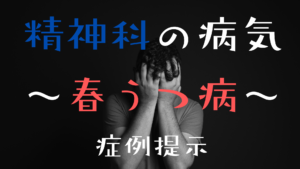

コメント